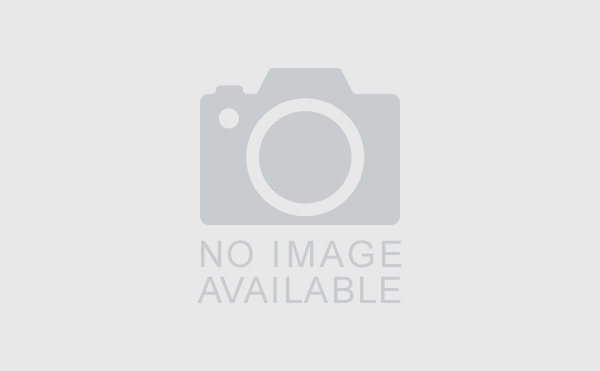お便り/12月号の未掲載分
トロント秋の風物詩「産卵で遡上するサーモンたち」
ジミー狩野(牧男)85歳 カナダ・トロント
大都会のド真ん中を流れる川で、産卵のために遡上するキング・サーモンを見られるのは世界広しといえどカナダのトロントぐらいだろう。トロントでは夏の終わり頃からキング・サーモンの遡上 (サーモン・ラン、Salmon run) が始まる。 トロントはオンタリオ州の州都であり、カナダ最大の都会だ。トロント大都市圏(GTA)の人口は約625万人という。トロントの目の前に広がるのはオンタリオ湖だ。五大湖でも一番小さい湖だが、水平線の彼方には対岸が見えないほど海のように広い。 もともとオンタリオ湖をはじめ五大湖には太平洋側のサーモン類は生息していなかった。1885年11月にカナダ横断鉄道の開通を記念してキング・サーモンとコーホー・サーモンの稚魚たちがブリテッシュ・コロンビア州(B.C 州)より遥々と横断鉄道で運ばれて来てオンタリオ湖に放流された。 太平洋側のサーモンたちは、キング・サーモン(和名;マスノスケ)やコーホー・サーモン(和名;ギンザケ)、他にピンク・サーモン(和名;カラフトマス)、サッカイ・サーモン(和名;ベニザケ)とホワイト・サーモン(和名;シロザケ)の5種だ。次々とこれらのサーモン類がB.C州より運ばれオンタリオ湖に放流され、それらは代々五大湖で成長し繁殖している。この他、同じ頃にオンタリオ湖に放流されたニジマスとスティールヘッド(降海型ニジマス)が生息している。 元来オンタリオ湖には原産のレイクトラウトや大西洋側のアトランティック・サーモンが生息していた。しかし、1898年頃には乱獲のためオンタリオ湖のアトランティック・サーモンは絶滅した。近年になって「オンタリオ湖アトランティック・サーモン復元プログラム」がスタートし、トロント東方郊外の川に稚魚が放流された。それが今では大きく成長しオンタリオ湖の復元プログラムは成功している。しかし、太平洋側のサーモンたちと大西洋側のアトランティック・サーモンは、同じ水域では生息しないと言われて来た。だが、オンタリオ湖だけは世界でも稀に唯一同居している。これは学術的に非常に珍しいことだと言われている。ちなみに、オンタリオ湖原産のレイクトラウトは、明治初期にトロントから日本に行ったキリスト教宣教師によって日光中尊寺湖に稚魚が放流され、それが現在「幻の魚」と言われるほど巨大な魚に成長している。その後、カナダ・ブリテッシュ・コロンビア州からニジマスとスティールヘッドの稚魚が日本へ運ばれこれは食糧用にと放流された。それが今では日本全国で繁殖している。とくに、箱根芦ノ湖のスティールヘッド(スーパー・トラウト)が有名。なお、1966年に日本の北海道産サクラマスがオンタリオ州北部の原野アルゴンキン・パークに放流された。しかし、サクラマスは少数しか定着せず、1970年代には確認されなくなった。 ところで、不思議なことに、どうしてサーモンたちは間違いなく産まれた母川に帰って来れるのだろうか。この回帰性と呼ばれる習性の秘密はいったいどのような仕組みなのか。産まれた川の臭いでわかるという「臭覚回帰説」や、太陽の位置などを目安に帰る「太陽コンパス説」、その他に「地磁気説」や「海流説」などが挙げられる。ただ実際はどうなっているのかまだ解明されていない。とくに、オンタリオ湖のサーモンたちの回帰性を、私は「湖水流説」の習性を強く信じている。 さて、オンタリオ湖は東西にその距離が310kmあり南北は85kmある。水深は最も深いところで244mもあり、それはオンタリオ湖の南東部に位置する。なお、オンタリオ湖の北側はカナダ・オンタリオ州に、南側はアメリカ合衆国ニューヨーク州へと接している。オンタリオ湖への代表的な河川の流入は、南西部のカナダ側とアメリカ側の国境にあるナイアガラ川から常に膨大な水量がエリー湖から流れ出ている。それがナイアガラの滝を通過しオンタリオ湖へと注がれる。その他、オンタリオ湖への流入河川は沢山あるがすべてセント・ローレンス川へ流れ出て、大西洋へとつながっている。 膨大なナイアガラ川の水流はオンタリオ湖へ注いだ後、オンタリオ湖の南側を、ようするにアメリカ側を東へと移動しやがてセント・ローレンス川に流れ出る。ただ、その反動で一部水流がオンタリオ湖を北へ流れ、北側では西回り(時計の逆回り)の水流が発生する。なお、オンタリオ湖の水が全部入れ替わるのに約6年もかかるといわれている。 太平洋側のサーモンたちは川で産まれ海で大きくなって母川へ帰ってくるのだが、五大湖のサーモンたちは海には行かず、五大湖で大きくなるので完全に「淡水陸封型」なのだ。海のサーモンたちにはトドやアザラシといった天敵が容赦なく襲いかかってくるが、オンタリオ湖に生息するサーモンたちの天敵は「釣り師たち」なのだ。 さて、オンタリオ湖のキング・サーモンの一生は、夏の終わり頃からトロント周辺の川を産卵のために遡上し、川底が砂利でしかも湧き水が出る所を探し、そんな場所を見つけるとメスが尾鰭で砂利をかき分け卵を産むくぼみ(産卵床)を掘る。そして何匹かのオスたちが1匹のメスに寄り添い産卵・放精を行う。(オスたちがメスをかばうので、キング・サーモンのメスを釣るのは至難の業だ。)産卵が終わると、7日から10日ほどでオスもメスも生き絶えて死んでしまう。(コーホー・サーモンは紅葉シーズンが終わる10月末頃から遡上を始め、12月末になっても産卵が続く。) 水温にあまり変化の少ない湧水の湧き出るところに産卵された卵は砂利のくぼみの中に留まり、毎日の水温を足した数値が480℃になると孵化し、さらに480℃に相当する日数が経つと稚魚となって砂利のくぼみから出て移動を始める。例えば、湧水の水温が8℃だと60日で孵化し、さらに60日で稚魚となるわけだ。砂利のくぼみから出た稚魚は、川の中のプランクトンや微生物、そして昆虫などを餌として成長する。しかし、逆に大きな魚に喰われることもあるので、稚魚の数は半減以下となってしまう。少しづつ成長したキング・サーモンの稚魚は、雪解けの春3月頃から5月にかけて河川からオンタリオ湖へと出て流れに沿って移動する。キング・サーモンの稚魚たちは時計の逆回りに水流と一緒に4~5年の旅に出るのだ。 やがて稚魚たちは湖水の流れに沿ってカナダ側から西へと向かい、西から南、そして南側のアメリカ側を東に回遊を続け、やがてオンタリオ湖南東にある244mの最深部(オンタリオ州キングストンの対岸でアメリカ側)に到達し、そこで飽食しながら3~4年で大きく成長する。 ところで、オンタリオ湖にはサーモンたちの餌となるニシン科の一種でエールワイフや日本のワカサギやししゃもに似たキュウリウオ科のスメルトという体長30cmぐらいの外来種の魚が生息している。(五大湖のキング・サーモンたちはこのエールワイフやスメルとを飽食するので短期間で巨大化するといわれている。)なお、エールワイフもスメルトも元々大西洋に生息していたが、セントローレンス運河を通じて大西洋から五大湖に侵入し、現在は淡水陸封型となって五大湖で繁殖している。じつは、五大湖で繁殖したエールワイフは、大増殖によって五大湖の生態系に大きな影響を与え在来種のレークトラウトの減少や湖岸に大量の死骸が漂着するなどの問題を引き起こした。このためこの問題を解決するために太平洋側のキング・サーモンやコーホー・サーモンの他に、ピンク・サーモン、サッカイ・サーモンとホワイト・サーモンなどとレインボー・トラウトやステイールヘッドが放流された。ちなみに、エールワイフとは、その姿形から「太った女将」を意味する「エール・ワイフ」(ale - wife) と名付けられたという。 やがて大きく成長したキング・サーモンたちは、最深部に到達してから3〜4年で産卵期を迎える。産卵期を迎えたキング・サーモンたちはその深みから出て再び時計の逆回りの流れに沿って西へ移動し、初夏になるとトロント近辺に到達する。そして秋になるとキング・サーモンたちは餌を獲るのをやめ産卵の準備を始める。しかし、カエデの葉が紅葉し真っ赤になる頃をピークに産まれた川に戻って来て産卵をする。そして、産卵を終えたキング・サーモンたちの一生が終わる。 トロント周辺でキング・サーモンとコーホー・サーモンの稚魚を放流する川は、トロント西郊外の「クレジット川」がとくに有名だ。(レインボー・トラウトやスティールヘッドはトロント東部のポート・ホープという町の中を流れるガナラスカ川が放流で有名だが、アトランティック・サーモンはトロント東部郊外で釣り人たちの少ない、すなわち天敵のいないウイルモット・クリークに放流されている。)特にキング・サーモンの遡上で有名なのはトロント西郊外ミシサガ市を流れる「クレジット川」が有名で、地元釣り師たちはもちろん、外国からの釣り人たちや見物人も多く集まる。 この川でのキング・サーモン釣りは、日本の釣り雑誌や日本の釣りテレビ番組で私は何度も紹介した。私はこのクレジット川に50年以上通っているが、釣り仲間も多い。よく安倍寛信さん(元内閣総理大臣故安倍晋三氏と元防衛大臣岸信夫氏のお兄さん)ともご一緒した。紅葉の時期は日本からのキング・サーモン釣りのお客さんも多い。また有名タレントや芸能人らも数えきれないほどお連れしガイドした。 その中でどうしても忘れられないのは、元スポーツ庁長官「鈴木大地さん」が釣った巨大なキング・サーモンだ。彼は1988年ソウルオリンピックの100m背泳ぎで金メダルを獲得した鈴木大地さんだ。彼はそのご褒美に文藝春秋社から「カナダ原野アドベンチャー・フィッシング」に招待され、そのガイド役にこの私に白羽の矢が当たった。私は彼ら取材陣一行を小型水上飛行機2機に分乗させ、しかも大型カヌーを飛行機の横に取り付けて原野へ飛び立った。まるでアクロバット飛行のようにカヌーの風圧で斜めに飛んで行く。しかもキャンプ道具一式、炊事道具と食料品などを重量制限ギリギリに積み込み、10日間のカナダ・オンタリオ州最北端でハドソン湾近くへアドベンチャー・フィッシングに出掛けた。その様子は、スポーツ雑誌「Number / ナンバー」(平成2年12月15日号)に掲載された。鈴木大地さんが記事を書く予定だが、雑誌編集長の谷口和人さん以下写真家の佐貫直哉さんとスタッフ全員が沢山魚を釣りり上げているのに、どうゆうわけか肝心の鈴木大地さんにだけ釣りの女神は微笑んではくれなかった。一行は「本人が釣れなきゃ絵にならない!」と途方に暮れていた。とうとうカナダ滞在最終日で明日は日本へ帰国という日になり、私は彼にどうしても巨大なキング・サーモンを釣らせたくて早朝の夜明け前からトロント西郊外のクレジット川へ案内した。一日中彼は頑張ってくれた。だが、その日もボウズのまま終わろうとしていた。夕方になり最後の最後に彼はなんと推定40ポンド(約18kg)オーバーの超大物を仕留めたのだ。その時、大役を果たした私は安堵感と喜びのあまり大粒の涙が私の頬を濡らしていた。計測すると体長1m5cm、巨大なキング・サーモンのオスだ。それを抱え満面の笑みをたたえ夕陽に照らされた鈴木大地さんの顔が忘れられない。未だにその思い出がいつまでも脳裏に浮かんで来るのだ。